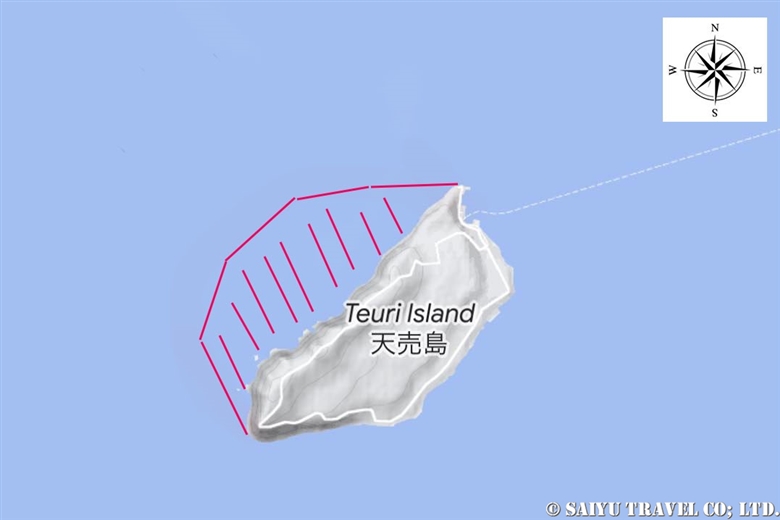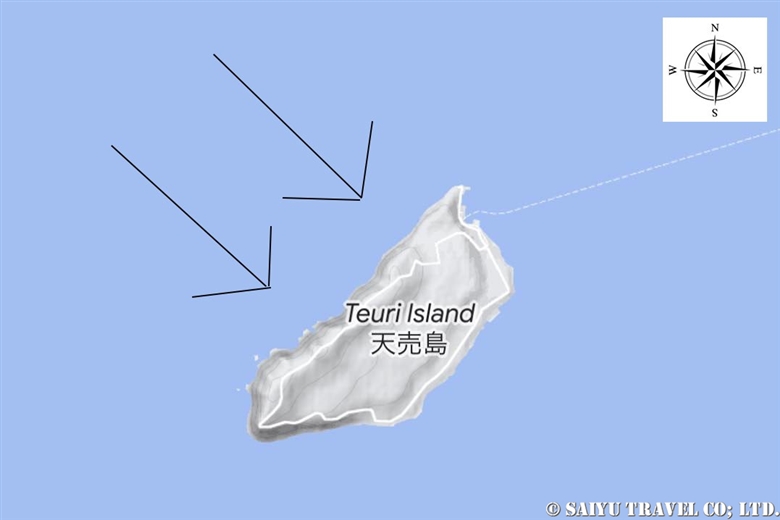生物多様性の宝庫、マダガスカル。見られる全動植物種の約90%が世界でマダガスカルにしか生息しない固有種であるため、観察場所を変えるたびにライファーと出合います。日中の観察で出会った生き物の一部をご紹介します。
ワオキツネザル:Ring-tailed lemur、Lemur catta
メスがグループのリーダーで、今回訪れた10月の繁殖期には子供を背中に乗せたメスが群れの先頭を歩く姿が見られました。ワオキツネザルを含む、キツネザルの仲間は体温調節が得意ではなく、早朝などは日が出ると日光浴する姿も観察できるそうです。

子供を背中に乗せたメスのワオキツネザル (Ring-tailed lemur、Lemur catta)
ベローシファカ:Verreaux’s sifaka、Propithecus verreauxi
地面を歩くときなどは、横向きにジャンプしながら移動します。サボテンの多く存在する場所にも生息する為、人間ではとても触れないトゲの枝にもしっかりとつかまって生活する姿が印象的でした。

横向きにジャンプしながら移動するベローシファカ (Verreaux’s sifaka、Propithecus verreauxi)

ベローシファカ (Verreaux’s sifaka、Propithecus verreauxi)
カメレオンの仲間
世界に生息する60%のカメレオンは、マダガスカルに生息しています。世界で一番重たいカメレオンである、パーソンカメレオン(Parson’s chamaeleon, Calumma parsonii)や、ゾウのように大きな耳が特徴なゾウカメレオン(Elephant Ear Chameleon, Calumma brevicorne)、地域によってさまざまな色合いを持つパンサーカメレオン(など多種多様なカメレオンたちを観察することができました。

パンサーカメレオン(Panther chameleon, Furcifer pardalis )

ゾウカメレオン(Elephant Ear Chameleon, Calumma brevicorne)
マダガスカルアデガエル :Madagascan mantella, Mantella madagascariensis
中南米などに生息するヤドクガエルなどと同様に体に毒があることを警告する為に、非常にきれいな体色をしています。

マダガスカルアデガエル (Madagascan mantella, Mantella madagascariensis )
マダガスカルヤツガシラ :Madagascar hoopoe, Upupa marginata
ヤツガシラの多くは、渡り鳥として有名ですが本種は渡りをしないマダガスカル固有種です。日本などで観察できるものに比べて、オレンジ色が非常に濃く色合いがとても綺麗です。

マダガスカルヤツガシラ (Madagascar hoopoe, Upupa marginata )
ルリガシラハシリジブッポウソウ:Pitta-like Ground Roller, Atelornis pittoides
英名が、Pitta-like Ground Roller(ヤイロチョウのようなジブッポウソウの意味)で、その名の通り地面の上をピョンピョンと跳ねる姿はまるでヤイロチョウのようです。きらきらと輝く青色が非常に美しく多くのマダガスカルの野鳥図鑑の表紙を飾っている鳥です。

ルリガシラハシリジブッポウソウ (Pitta-like Ground Roller, Atelornis pittoides )
ヒルヤモリの仲間
ヤモリは、夜行性の種類が多い中で昼に活動する種はヒルヤモリと呼ばれます。昼の生活でも擬態をする為、緑色をしている種類が非常に多いのが特徴的です。ヨツメヒルヤモリ (Four Spot Day Gecko, Phelsuma quadriocellata )、グランディスヒルヤモリ (Madagascar Giant Day Gecko, Phelsuma madagascariensis )など多くの種類を観察することができました。

ヨツメヒルヤモリ (Four Spot Day Gecko, Phelsuma quadriocellata )
キリンクビナガオトシブミ :Giraffe Weevil, Trachelophorus giraffa
キリンのように長い首を持つオトシブミの仲間です。卵を産んだ後、幼虫のえさとなる葉で卵を包み込み、木から切り離して地面に落としてしまう姿の観察にも成功しました!

キリンクビナガオトシブミ (Giraffe Weevil, Trachelophorus giraffa )
マダガスカルの動物というとキツネザルの仲間が有名ですが、日中に見られるさまざまな生き物を紹介させていただきました。次回は、夜のマダガスカルの生き物です!
Photo & text : Wataru HIMENO
Observation : Oct 2023, Madagascar
★西遊旅行のワイルドライフツアー一覧はこちら
★Youtubeでもワイルドライフの動画を配信しています。再生リストもご覧ください。