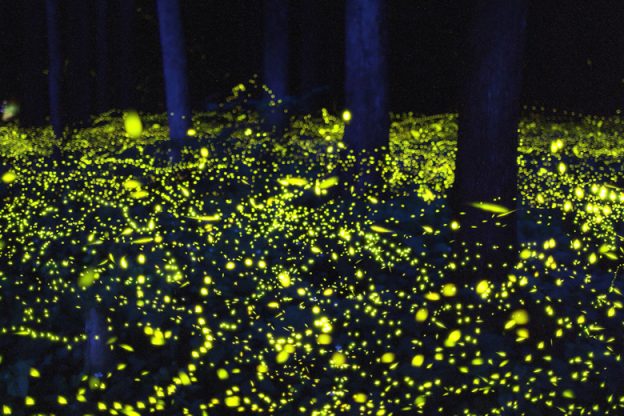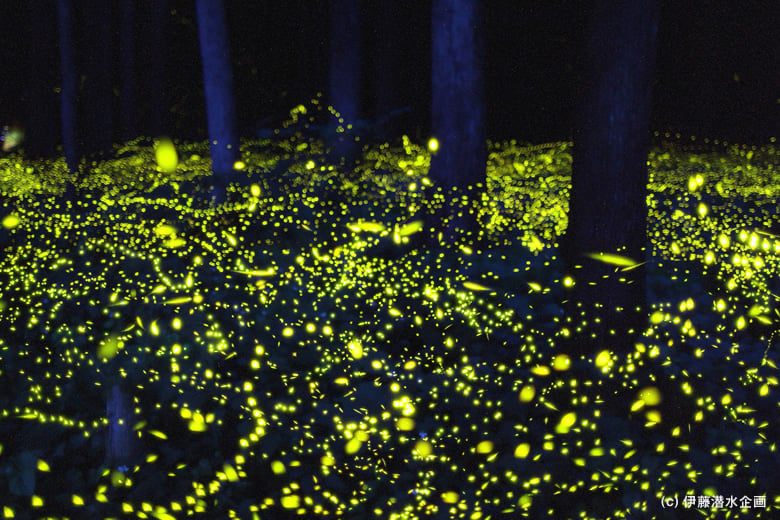インドのアッサム州にあるカジランガ国立公園で、鎧(ヨロイ)のような分厚い皮膚が特徴のインドサイに出会えました。その見た目から「ヨロイサイ」とも呼ばれます。 陸上の哺乳類では世界で最も皮膚が分厚く硬いといわれ、その厚さは最大4cmにも及びます。

英語では「大きな一角のサイ(Greater One-Horned Rhinoceros)」や「インドのサイ(Indian Rhinoceros)」と呼ばれます。2本の角を持つアフリカのシロサイやクロサイとは異なり、角が1本だけなのがインドサイの特徴です。同じアジアのジャワサイも角は1本で、こちらは「小さい一角のサイ(Lesser One-Horned Rhinoceros)」と呼ばれています。

(↑写真は角の長い個体です)
角は一生伸び続け、オスなどの長い個体では60cm以上になることもあります。 1900年代初頭には絶滅の危機に瀕していたインドサイですが、現在は回復傾向にあります。2022年の調査では個体数は4,014頭とされ、そのうち全体の約65%(2,613頭)が、ここカジランガ国立公園に密集して生息しています。

今回は2日間だけのサファリでしたが、延べ100頭近くのインドサイに出会えました。上の写真の時は湖の対岸で距離はありましたが、数えてみると一度に37頭ものサイを一望できました。


サファリ中には親子のインドサイも見られました。インドサイは繫殖期のカップルと子育て中の母子を除いて、基本的に単独で暮らします。

親子で仲良く草を食べます。

ゴツゴツしたインドサイも、子供はやはり可愛いですね。

3頭が一度に集まるシーンもありましたが、特に争いは起きず仲良く草を食べていました。オスは縄張り意識が強く戦うこともあるそうですが、メス同士は比較的穏やかな関係を保っているようです。
カジランガ国立公園では、早朝に「エレファント・サファリ(ゾウに乗ってのサファリ)」も楽しめます。

ジープサファリとは違い道路以外も進めること、そしてサイに近づいても警戒されにくいのがゾウ・サファリの魅力です。

早朝のサファリだったため、まだ眠そうに横になっているインドサイに遭遇しました。眠っているところを起こしてしまい、可哀想なことをしました。

シロサイやクロサイには泳ぐイメージがあまりありませんが、インド有数の大河・ブラマプトラ川流域で暮らすインドサイは泳ぎが非常に得意です。 よく「カバは泳げず、水底を蹴って進む」と言われますが、観察しているとインドサイはしっかりと体を浮かせて泳いでいました。

↑の写真で濡れているところを見ると、目耳鼻に水が入らないように泳いできた事がわかります。

背中にアマサギを乗せている個体もいました。サイが歩くときに草むらから飛び出す虫を、背中の上から狙っているのです。

カジランガのガイドさんによると、インドサイも特定の場所で排泄する「ため糞」の習性があるそうです。

インド政府による保護活動が進み、個体数も年々増えているとのこと。 ブラマプトラ川のほとりで力強く、そしてのんびりと暮らすインドサイを見ることができ、大満足のサファリとなりました。
Photo & Text : Wataru YAMOTO
Observation : Nov 2025, Kaziranga National Park, Assam, India
★西遊旅行のワイルドライフツアー一覧はこちら
★Youtubeでもワイルドライフの動画を配信しています。再生リストもご覧ください。