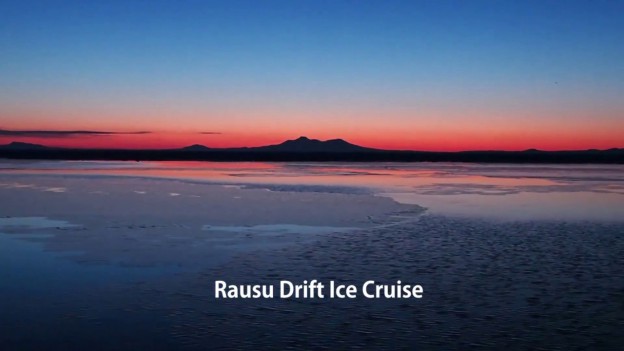12月下旬、パキスタンのクンジュラブ国立公園へ行ってきました。
到着した日は雪はなかったのですが大変冷たい風が吹き、中国との国境クンジュラブ峠4,700m付近ではマイナス30度。冷たい空気が鼻の奥に入り、「痛い」と感じるものでした。
以前には考えられなかったことですが、こんな季節にも観光客が訪れるようになり、峠にはラホールから来た新婚旅行の夫婦も。スーパームスリムなこのご夫婦はアッラーの作り出した偉大な自然の姿にとても感動されていらっしゃいました。
「厳冬のクンジュラブ国立公園」の景色と出会ったワイルドライフ
この数年、いろいろ教えてもらっているクンジュラブ国立公園のゴハール氏の案内で国立公園内のレンジャー施設に滞在させていただきました。
カラコルムの峻険な山に囲まれた小屋の滞在。すべてのものが凍る環境で食事を作りお皿を洗うこと、ブハリ(暖炉)に中国産の石炭をいれて火をつけること、水も氷る環境でのトイレ・・・何もかもが貴重な体験でした。

12月~1月はアイベックス Himalayan Ibex が交尾で標高の低いところへ降りてきます。そのためカラコルムハイウェイ沿いからアイベックスの群れを観察できます。メスを追うオスの姿が。

朝早い時間はカラコルムハイウェイ上をイワシャコ Chukar Partridge が横切ることが多いです。この鳥、パキスタンの国鳥です。

クンジュラブ峠へ向かう途中、トンネル付近でカラスが飛び立ったので見に行ったらヤクがユキヒョウに襲われていました。夕方、ユキヒョウが現れないか待ってみましたが、姿を見ることはありませんでした。

そして上空にはヒゲワシ Bearded vulture (Lammergeier) の姿。

クンジュラブ川にはカワガラス Brown Dipper が。冬に観察しやすい鳥です。

クンジュラブ峠を目指し標高を上げると川は完全に凍っていました。

途中、山肌から水が吹き出しているところが凍り、道路がツルツルに氷り危ない箇所も。

クンジュラブ川の氷の上を少し歩いてみました。これはちょっと不思議な光景。

冬のクンジュラブ峠、中国との国境です。スストの人たちの話では、国境は2018年11月30日まで開いていました。春はこれまで5月1日から外国人の通行が可能でしたが、2019年は雪の状況が許せば4月1日からという話です。

ゴハール氏がヒマラヤセッケイ Himalayan Snowcock を探そうというので国境の付近のカラコルムハイウェイから登りました。すでに4,700m付近にいたのでこの登りもしんどいものです。

苦労は報われずヒマラヤセッケイを探すことはできませんでしたが、雪に覆われたクンジュラブ峠の中国との国境を臨むことができました。

翌日、早朝に見つけた新しいユキヒョウの足跡。カラコルムハイウェイを横断してアイベックスの群れのいる方向へ足跡が続いていました。ゴハール氏が足跡を追いましたが見つけることはできませんでした。
Photo & Text : Mariko SAWADA 澤田真理子
Observation: Khunjerab National Park, Pakistan
Reference : Mr.Sultan Gohar -KNP (Khunjerab National Park)