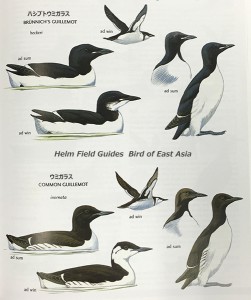ミャンマーのインレー湖で出会ったオオバンたちです。
オオバン(Common Coot またはEurasian Cootとも)は夏はユーラシア大陸北部の湖沼地帯で繁殖し、夏に東南アジア、アラビア半島、アフリカの一部、そして日本に渡り越冬します。日本では琵琶湖にで越冬するオオバンが増えた、とニュースで見たことがあります。
ミャンマーのシャン州にあるインレー湖にはInle Wetland Wildlife Sanctuary という野鳥保護区があります。以前はたくさんの野鳥が観察できたそうですが、インレー湖の「フローティング・ガーデン」で使用される農薬の影響で野鳥が減ってしまったとも言われています。

12月半ばのインレー湖です。厳しい朝もやの中、オオバンたちの群れに出会いました。この時期のインレー湖は朝から9時頃まで朝もやで覆われます。

私たちがボートで近づくとオオバンたちが水面を走り始めます。

大きな水かきのついた足で水面を走る姿は見事。

朝もやの中、ボートからオオバンを狙うカメラマンさんの姿。

このオオバン、一番気になるのは「足」。木の葉状の水かきがついています。

気になる「木の葉状の水かき」の足。

水面を走るように飛び立っていく姿は何度見ても、何度見ても飽きません。

朝もやが上がりました。チュウサギ Intermediate Egretのそばをオオバンの団体さんが泳いでいきます。冬の季節のインレー湖は朝9時ごろまでは霧で覆われていますが徐々に晴れてきました。

オオバンたちが、晴れたインレー湖の空に飛び立っていきました。
Photo & Text : Mariko SAWADA 澤田真理子
Observation : Dec 2015, Inle Lake, Shan State, Myanmar
Reference : Helm Field Guids” Birds of South East Asia”, Birds of Myanmar, Wikipedia(JP)