こんにちは大阪支社の高橋です。
今回は、カーボヴェルデの中でも最も火山活動が活発な島「フォゴ島」についてご紹介したいと思います。
「カーボヴェルデ」という国名を聞いて、いったいどこなのか・・・そう思われた方が多いのではないでしょうか。まずは、カーボヴェルデという国についてご紹介します。国の正式名称は「カーボヴェルデ共和国」と言い、大西洋の中央、セネガルの首都ダカールがある「カップ・ヴェール岬」より約500km、北アフリカの西沖合のマカロネシアに位置するバルラヴェント諸島(風上諸島)とソタヴェント諸島(風下諸島)からなる共和制の国家です。15世紀~1975年までポルトガル領であった時代もあり、独立に際してアフリカ大陸部のギニアビサウと統合する計画がありましたが、1980年のギニアビサウでのクーデターによって連合構想は破綻し現在に至ります。史跡としてはイギリスのフランシス・ドレークをはじめ多くの海賊や外国の脅威にさらされ、破壊された町シダーデ・ヴェーリャが残っています。
カーボヴェルデは、10の島(内9は人が居住。サンタ・ルシア島には定住者がいない)と8の小島で構成され、地質学的にはプレートの運動により大西洋が拡大中に、ホットスポットでマントルの部分融解融で発生したマグマが噴出した玄武岩類が諸島を形成したとされています。現在の島を構成するのは2千万年前から8百万年前の火山岩であると言われています。大小15の火山群島からなるカーボヴェルデ。その中でも最も火山活動が活発な島が「フォゴ島」であり、そのフォゴ島での最大の見所と言えば「フォゴ国立公園」であります。
 フォゴ国立公園エリアに入るとすぐ目の前に聳えるカノ火山
フォゴ国立公園エリアに入るとすぐ目の前に聳えるカノ火山
フォゴ島は、ホットスポットによって形成されたカーボヴェルデ諸島において最も若い火山島で、諸島の西端部に位置しています。ホットスポットで順次作られた活火山がアフリカプレートに乗ってホットスポットの上を東に向かって移動し多島海を形成しています。フォゴ島は1つの火山から成り、島は直径約25キロメートルのほぼ円形というかたちをしています。1995年に起きた噴火活動で、ピコ・レケノという新たなクレーターが出現しました。カルデラは最大9kmの幅があり、外縁は1kmの高さを誇ります。巨大な山頂部はカルデラの中央部にあり、カノ火山(フォゴ山)と呼ばれて、活発な成層火山であり、カーボヴェルデ共和国最高峰の標高2829メートルの山であります。山頂はカルデラの外縁より100mほど高く、火口からの溶岩は、島東海岸に達しました。
 中央が「カノ火山(2829m)」 右麓の丘が1995年の溶岩滴丘、その麓が当時の溶岩流跡、左麓、雲の下に小高く広がる丘が2014年の噴火口
中央が「カノ火山(2829m)」 右麓の丘が1995年の溶岩滴丘、その麓が当時の溶岩流跡、左麓、雲の下に小高く広がる丘が2014年の噴火口
近年の噴火は2014年11月で、中央火口丘側面での噴火がありました。当時のニュースでは、周辺住民数百人に「コミュニティの人々はチャダスカルディラスを放棄するよう」と、ホセ・マリア・ネベス首相の指示に従うよう避難を呼びかけていました。データによると、噴火は1995年(1995年の噴火は、4月2日から3日にかけての晩に始まり、島は火山灰の噴煙に覆われました)のそれに匹敵するか、それより強大で、物事がさらに悪化する可能性がある、とネベス首相は述べています。
 カルデラの外縁、その麓は2014年の溶岩流
カルデラの外縁、その麓は2014年の溶岩流
カルデラ内へ車を走らせ、2014年の噴火の影響で道路が寸断されているポイントまで向かいます。道路上には冷え固まった溶岩流が覆いかぶさっており、黒光りしている溶岩石などをガイドさんが採取してくれました。その後、青空の下、山裾がキレイに広がるカノ山の山容を堪能するため、山麓の散策を楽しみます。
 溶岩石を採取するフォゴ島のガイドさん
溶岩石を採取するフォゴ島のガイドさん
 カノ山の麓の散策を楽しむみなさん
カノ山の麓の散策を楽しむみなさん
散策を楽しんでいると、と左右に大小の窪みのあるポイントがいくつも見られました。不思議な窪みのためガイドさんに聞いてみると、これらは以前木が植わっていた跡だったそうです。
 不思議な窪み
不思議な窪み
一見溶岩石に覆われているため気付かないのですが、実はこのカルデラ内の土地は肥沃な土地であり、農業が営まれていた場所だったそうです。降水量が極端に少ないカーボヴェルデ、せっかく降った雨を余すことなく木々などのために利用するために考えられた方法で、木や作物をこうして窪みの真ん中に植え込むという方法が取られていたそうです。
 窪みの真ん中に植え込まれた苗木
窪みの真ん中に植え込まれた苗木
カノ火山の麓の散策では、のんびり景色を楽しまれる方々、せっかくのなので小さな溶岩滴丘へと登られる方など、思い思いに楽しまれていました。私も溶岩滴丘に登るグループに同行し、わずか10分ほどで登り切った丘の上からは、カルデラ内部に広がる雄大な景観、また過去の噴火の影響でできた溶岩流跡などを展望することができました。
 1995年の溶岩流跡
1995年の溶岩流跡
以前は寸断された道路の先にポルテラ村などいくつか村があったそうですが、2014年11月の噴火で村は全壊してしまい、溶岩流はポルテラの村の斜面を下り主要道路のひとつを覆い尽くし、200の家屋やスポーツセンターが溶岩流によって破壊されたとのことでした。噴火当時、カーボヴェルデのホセ・マリア・ネベス首相は数百人の周辺住民に避難をするよう呼びかけたそうで、幸いにも死者はでなかったそうです。
 2014年11月の噴火口
2014年11月の噴火口
散策をしていると、数名の男性が廃屋のようになった場所で作業を行っていたり、別の場所では窪みに小さな苗木が植わっていたりもしておりました。いつの日か、この地で農業が、人々の生活が再開される日がくるまもしれない。そう感じさせてくれる場面でもありました。
 散策中に目にした農業再生の気配
散策中に目にした農業再生の気配
その他、フォゴ島では「フォゴ・ワイン」と「フォゴ・コーヒー」が有名です。フォゴ島の北部に位置するレルヴァ(Relva)という小さな村で「フォゴ産のワイン」の工場見学をさせていただきました。まだ日本では馴染みのない「フォゴ産のワイン」ですが、赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン、何とアイスワインまで生産しており、希望のワインをそれぞれ試飲させていただきました。年間で100,000リットルも生産されているとの情報もあり、日本でたまたま訪れたレストランでカーボヴェルデ産のワインに出会う日があるかも、そんな時レストランで「現地のワイン工房で試飲させてもらったことがありますよ」などと言える日がそう遠くないかもしれません。
※私もフォゴ産の赤ワインを購入しました。

お勧めのフォゴ産赤ワイン
さらに東海岸線を北上し、フォゴ島南部に位置するモステイロス(Mosteiros)地区のFeijoal村では、「コーヒー工場」へと訪れます。村周辺の斜面にはコーヒープランテーションが広がっており、コーヒーの木の苗木がたくさん並んでおり、収穫したコーヒーの豆を天日干ししている風景も見られます。ここの工場では、天日干しした実を焙煎前の豆にまで仕上げる作業を行うとの事で、焙煎そのものはカーボヴェルデの別の島であるサンチャゴ島のプライアで行われているとの事でした。フォゴ島のコーヒーは、フォゴ産のワインとともに、お勧めの一品です。
※もちろん、私も購入し、毎朝飲んでいました。
 コーヒーの実を選別する女性
コーヒーの実を選別する女性
活発な火山活動を続ける成層火山「カノ火山」をご覧いただけるフォゴ国立公園、さらには、日本でも馴染みの少ないフォゴ産のワインやコーヒーなど。その他さまざまな景観・文化を堪能いただけるカーボヴェルデのフォゴ島はお勧めの島のひとつです。



































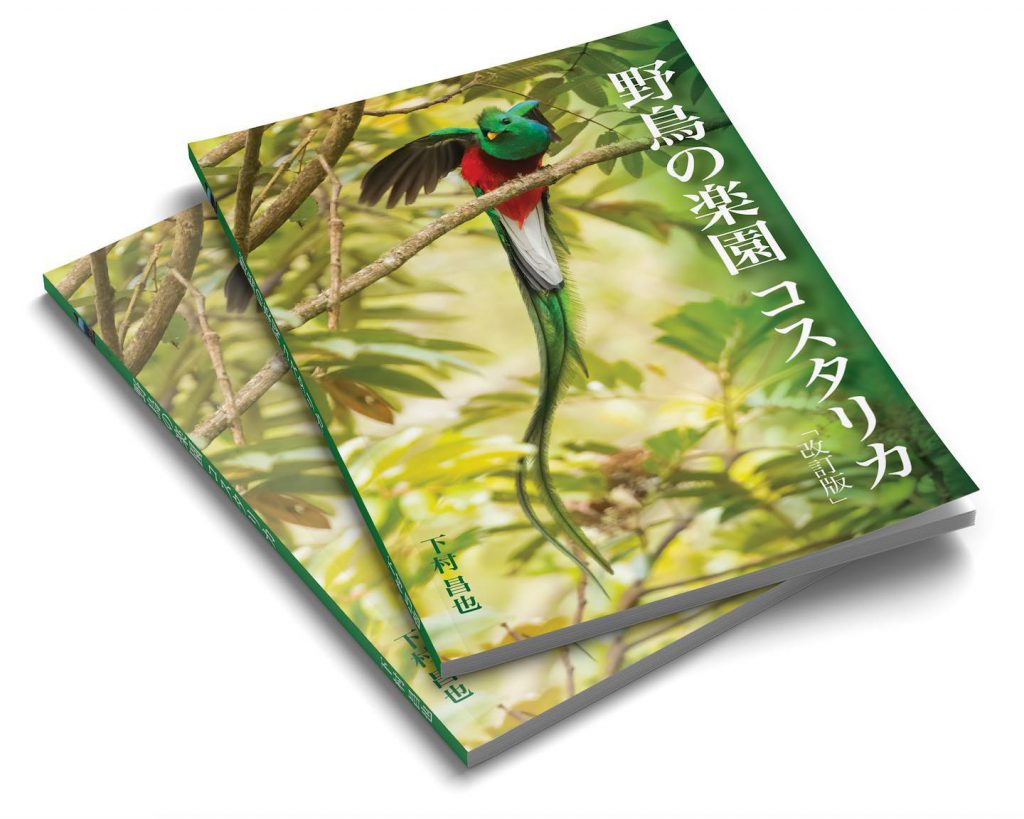
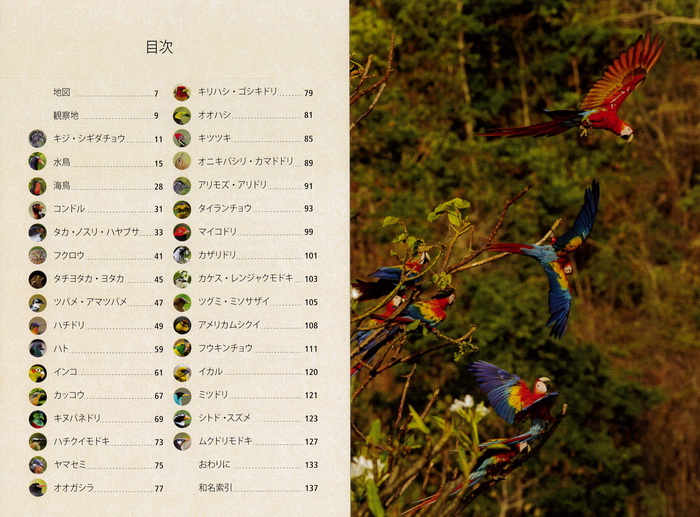
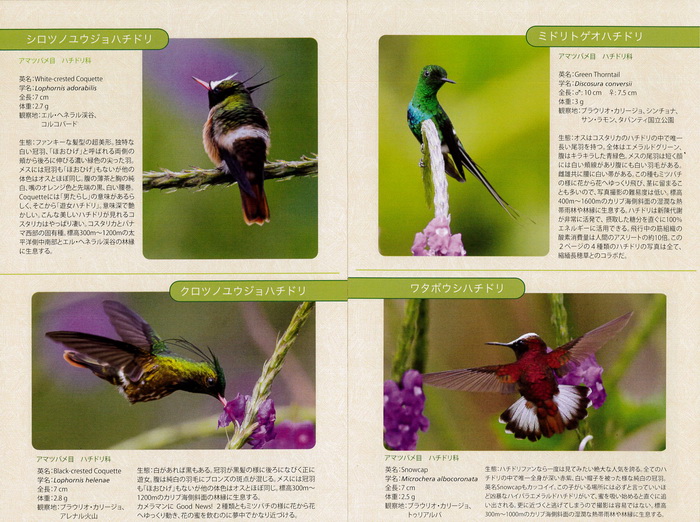
 フォゴ国立公園エリアに入るとすぐ目の前に聳えるカノ火山
フォゴ国立公園エリアに入るとすぐ目の前に聳えるカノ火山 中央が「カノ火山(2829m)」 右麓の丘が1995年の溶岩滴丘、その麓が当時の溶岩流跡、左麓、雲の下に小高く広がる丘が2014年の噴火口
中央が「カノ火山(2829m)」 右麓の丘が1995年の溶岩滴丘、その麓が当時の溶岩流跡、左麓、雲の下に小高く広がる丘が2014年の噴火口 カルデラの外縁、その麓は2014年の溶岩流
カルデラの外縁、その麓は2014年の溶岩流 溶岩石を採取するフォゴ島のガイドさん
溶岩石を採取するフォゴ島のガイドさん カノ山の麓の散策を楽しむみなさん
カノ山の麓の散策を楽しむみなさん 不思議な窪み
不思議な窪み 窪みの真ん中に植え込まれた苗木
窪みの真ん中に植え込まれた苗木 1995年の溶岩流跡
1995年の溶岩流跡 2014年11月の噴火口
2014年11月の噴火口 散策中に目にした農業再生の気配
散策中に目にした農業再生の気配
 コーヒーの実を選別する女性
コーヒーの実を選別する女性









 トンブクトゥへの道中であった塩を運ぶ人々
トンブクトゥへの道中であった塩を運ぶ人々 ジンガリベリ・モスク
ジンガリベリ・モスク サンコーレ・モスク
サンコーレ・モスク