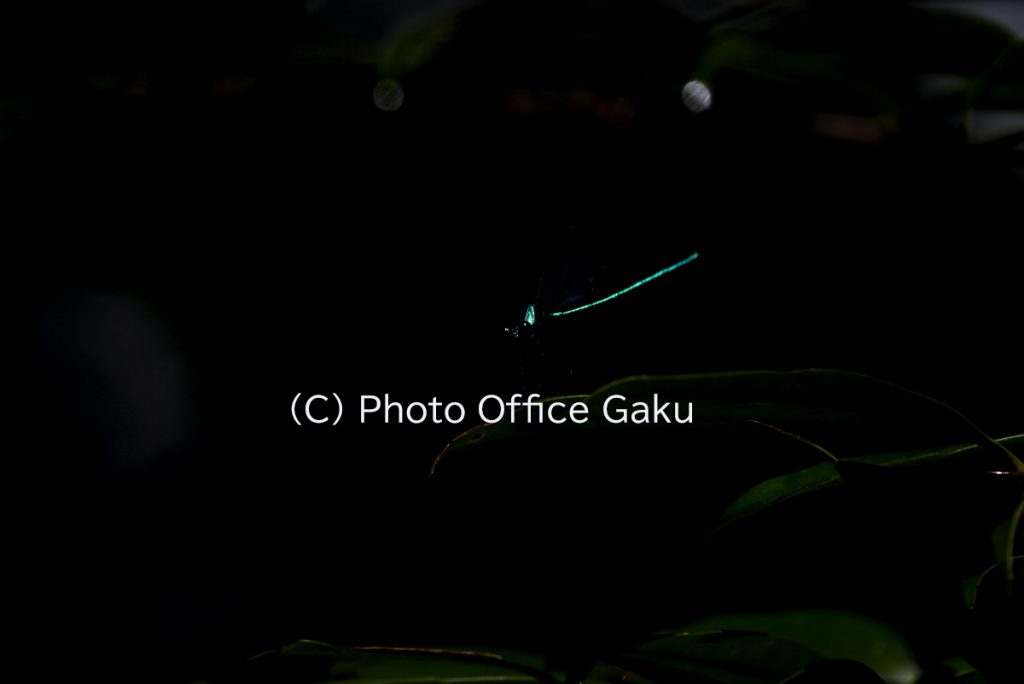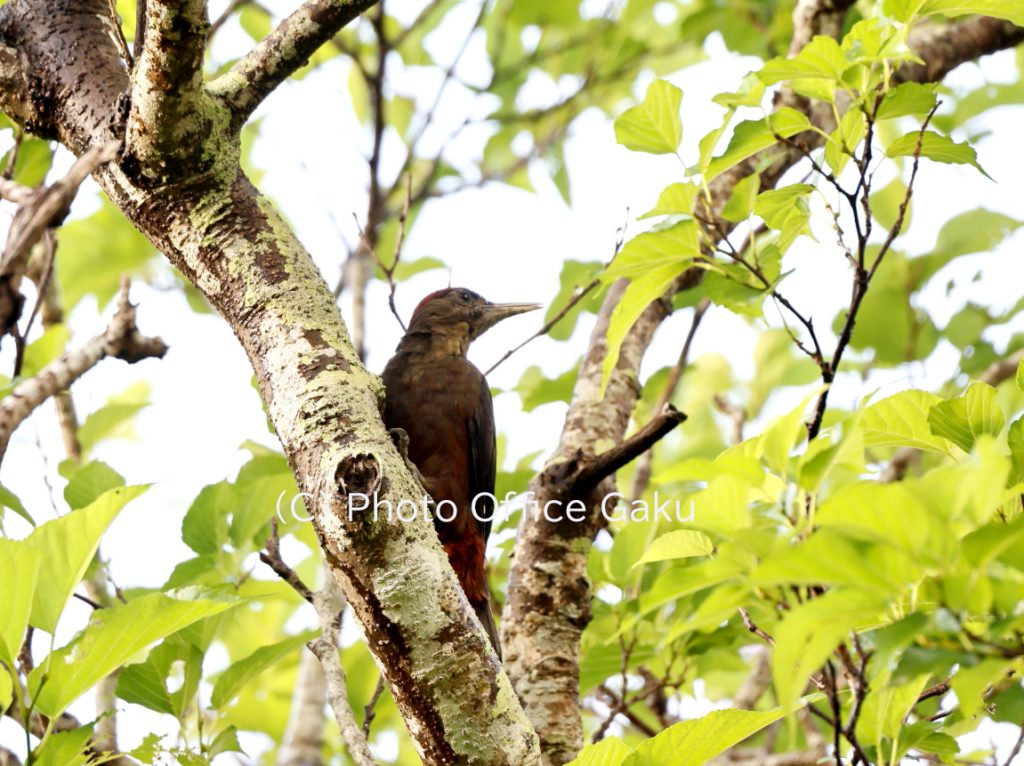今年は鳥インフルエンザの発生がまだだったので、現場での緊張感はさほどありませんでした。その分、入域証で入られる場所が決まっていて、東干拓と西干拓の観察ポイントを移動しながらの定点撮影でしたが、いろんな鳥たちの撮影ができました。
カツオドリは日によって数が増減する&風によっても飛び込む場所が変わるので、難しいものの、みなさん撮影を存分に楽しめたように感じました。
12月15日 1日目 鹿児島市 晴れ
空港で集合後、そのままカツオドリのポイントを目指します。その前に、近くにある物産館でお弁当を買ってもらいポイントへ向かいました。
下見の時は80羽ほどいたのですが、この日は30羽程度でした。残念だったのは、ダイビングをして魚をくわえて浮上するシーンが何度もあるのにほとんど失敗!あと風が悪く、飛び上がる方向が反対で80%が「ケツ撃ち」になってしまう事。それでも太陽が建物に隠れる16時30分まで粘りました。

12月16日 2日目 鹿児島市~出水市 晴れ
7時30分に出発をして出水に向かいます。今日は1日天気がいいのでこのチャンスを逃すわけにはいかない!
9時30分ごろ観察センターに到着、まずはレクチャーを受けてから2階に上がり撮影開始。ツルたちの動きを説明して撮影をしてもらいます。その間にコクマルガラス探しをしますが・・・見当たらない。水を張った田の周辺に白い塊を見つけたので確認をするとヘラシギとクロツラヘラサギだった。しかし遠い!
参加者が「サカツラガンがいる!」というのでツルの群れの中を見るといました!ただ距離があるので撮影にはちょっと厳しい。スコープを持ってきた方がいたのでみんなでスコープを覗き、拡大されたサカツラガンを堪能しました。ふと見上げると、ヘラサギたちの群れが青空バックで群れが飛んで行くのでしっかりと撮影ができました。


その後、何か白っぽい中型の鳥が横切ったので反射的に連写。よく見ると変なムクドリ?ギンムクドリかシベリアムクドリだが、とにかくみなさんに撮ってもらうと、隣にいた方が「すいません、あの上空の猛禽類は何ですか?」と。トビと絡んでいる白っぽいタカ?初列が黒く、灰色?全体的にコンパクト?・・・まさかのハイイロチュウヒのオスでした!

変なムクドリが飛び去り、ハイイロチュウヒもどこかに消えてしまうと「キャウ、キャウ」というかわいい声があちこちから聞こえる?電線にとまるミヤマガラスを見渡すと小ぶりなカラスがちらほら・・・。やはりコクマルガラスでした。かなりいるようだがその中から2羽の「パンダ」を見つけみんなで撮影。いやぁ~怒涛の撮影タイムとなりました。

一旦11時になったので、食堂が混む前に出発。みなさんをうどん屋さんに案内して肉ごぼ天うどんを堪能してもらいました。
午後は東干拓に移動。監視小屋へ向かう途中、ヒシクイを見つけたので撮影をしてもらいました。観察小屋の前に出るとクロヅルをゲット!しばらく同じ場所で粘っていると、ハイイロチュウヒやハイタカが何度も飛んでくれてしっかりと撮影ができました。
また、カモの群飛の中にツクシガモを見出すこともできました。カナダヅルは見つからなかったので、移動できる経路上で車を停めて撮影。その後、もう一度監視小屋の前に行くと少し離れた場所にカナダヅルが3羽。幼鳥は飛んで行ってしまいましたが、ペアはまったりしていたので、歩いて近づき無事こちらもゲット!



その後は夕日ポイントに移動して待ちます。
この日は暖かい事もあり、無数の蜘蛛が糸を伸ばし飛んでいたので、「これは」と期待。夕陽に草についた蜘蛛の糸が金色に輝くなかツルを入れたいのだが・・・主役がいない!それではと夕日にツルたちを入れる瞬間を待つがこれまたほとんど飛んでこない!それでも数回のチャンスを逃さないように撮ってもらい、空の色が抜けたところで終了となりました。

12月17日 3日目 出水市 快晴のち大雨のち晴れ
天気予報では1日雨予報だったが、朝から晴れている。予想外の展開に期待をしながら朝日ポイントへ移動して日の出を待つも、東の空にかかる雲が意外にも厚く、雲間から出る光を絡めた撮影をしてもらいます。
東干拓の観察小屋へ行くと、近くにカナダガンのペアがいたので、光もいいし、陽炎もないのでしっかりと撮影。その後、西干拓の観察センター屋上から、飛翔するツルたちを狙いますが・・・あまり飛ばない。ギンムクドリやコクマルガラスもいないかと探すも見つからない。そんな中、昨日サカツラガンを見つけた方がカリガネとマガンをまたしても発見!すごい。私がほとんど探す気がないのがばれてしまう(笑)とはいえやはり距離があり撮影は厳しかった。

10時30分まで晴れていたのに、あれよあれよと雲が広がり11時にはどん曇りになってしまった。食堂でちゃんぽんを食べていると、もの凄い大雨が!雨で撮影ができなかった場合は物産館でお買い物ののち、温泉を予定していたので、そうするかと店を出ると・・・晴れだして陽が射してきた。虹まで出ている。それならばと撮影に出ると、銀杏の木にたくさんの中型の鳥が鈴なりになっている?一旦Uターンして戻ると全部ホシムクドリだったので、車から降りて撮影してもらいました。

ここで、「キャウ、キャウ」というかわいい声があちこちから聞こえる?かなりの数のコクマルガラスの幼鳥。成鳥は見つからなかったが、成鳥に近い個体はいたので撮ってもらう。その時、何か白っぽい鳥が楠のてっぺんにとまったので、見るとギンムクドリだった!すぐに飛んで行ってしまい、向かった先を探していると再び雨が降り出したので終了。

全員が車内に入るともの凄い雨が!ギリギリセーフ。前が見えないような雨だったので撮影は中断して物産館へ。出水は柑橘類が名産なのでみなさんに楽しんでもらいます。さてこの後は温泉だなと思っていると・・・またしても雨が上がり、空が明るくなったので撮影続行です。
雨上がりのいい光なので車を停めつつ車内から撮影してもらいました。夕方は夕日がからめの撮影を期待しましたが、思った以上に雲が厚くなり夕日は雲の中に消えてしまい終了になりました。温泉は逃したものの、予想外の天気にみなさん満足されていました。
12月18日 最終日 鹿児島市 晴れ
雨上がりの朝、あたり一面に霧が立ち込めてはいるが、空全体を覆い隠すほどではなく程好い高さ。明るさを増す東の山並みをバックに、西から飛んで来る群れを狙っていると太陽が顔をのかせます。思った通り霞越しなので太陽が赤味を増し、眩しくない!そこに入るツルたちを狙いました。


太陽が高く昇りきってから監視小屋の前に行くと、クロヅルがいたので撮影することができました。ここで出水はおおむね終了なので観察センターにトイレに寄る途中、水路脇の田んぼに白い鳥が!クロツラヘラサギの若い個体でした。近くで撮影ができてみなさん喜んでました。

ここからは約2時間のドライブでカツオドリポイントへ向かいます。
天気がいいのですが、風が悪い。カツオドリ12~3羽が周辺を飛び回りダイブしますが、相変わらずどの個体が飛び込むかがわからず苦労。他にはカンムリカイツブリ、セグロカモメ、ミサゴなどが出るのでそれも撮ってもらいます。しかしほぼ手持ちで狙い続けるのはかなり疲れるので、2時間が限度でした。14時30分出発して空港に向かい、15時30分無事解散となりました。


天気が予想に反して、いい方に転がってくれたことでしっかりと撮影ができたと思います。出水ではどうしても移動制限があるため「定点」での撮影になる分、いろんな鳥との出会いがあり良かったです。
撮れた鳥
カンムリカイツブリ・カツオドリ・ヒドリガモ・マガモ・コガモ・ハシビロガモ・オナガガモ・カルガモ・アオサギ・ダイサギ・コサギ・オオバン・ヘラサギ・クロツラヘラサギ・カナダヅル・マナヅル・ナベヅル・クロヅル・タゲリ・イソシギ・タシギ・ハマシギ・ミサゴ・トビ・ハイイロチュウヒ・ハイタカ・チョウゲンボウ・コクマルガラス・ミヤマガラス・ホシムクドリ・ギンムクドリ・マガン・ヒシクイ・サカツラガン・カリガネ・ハクセキレイ
見られた&声を聞かれた鳥
カイツブリ・カワウ・キジバト・ドバト・ハヤブサ・セグロカモメ・ツクシガモ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ヒバリ・ヒヨドリ・スズメ・ハクセキレイ・キセキレイ・タヒバリ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・カワセミ・ツグミ・シロハラ・イタチジョウビタキ・オオバン・モズ・トビ・ノスリ・モズ・ヒバリ・タヒバリ・ムクドリ・ジョウビタキ・スズメ・カワラヒワ